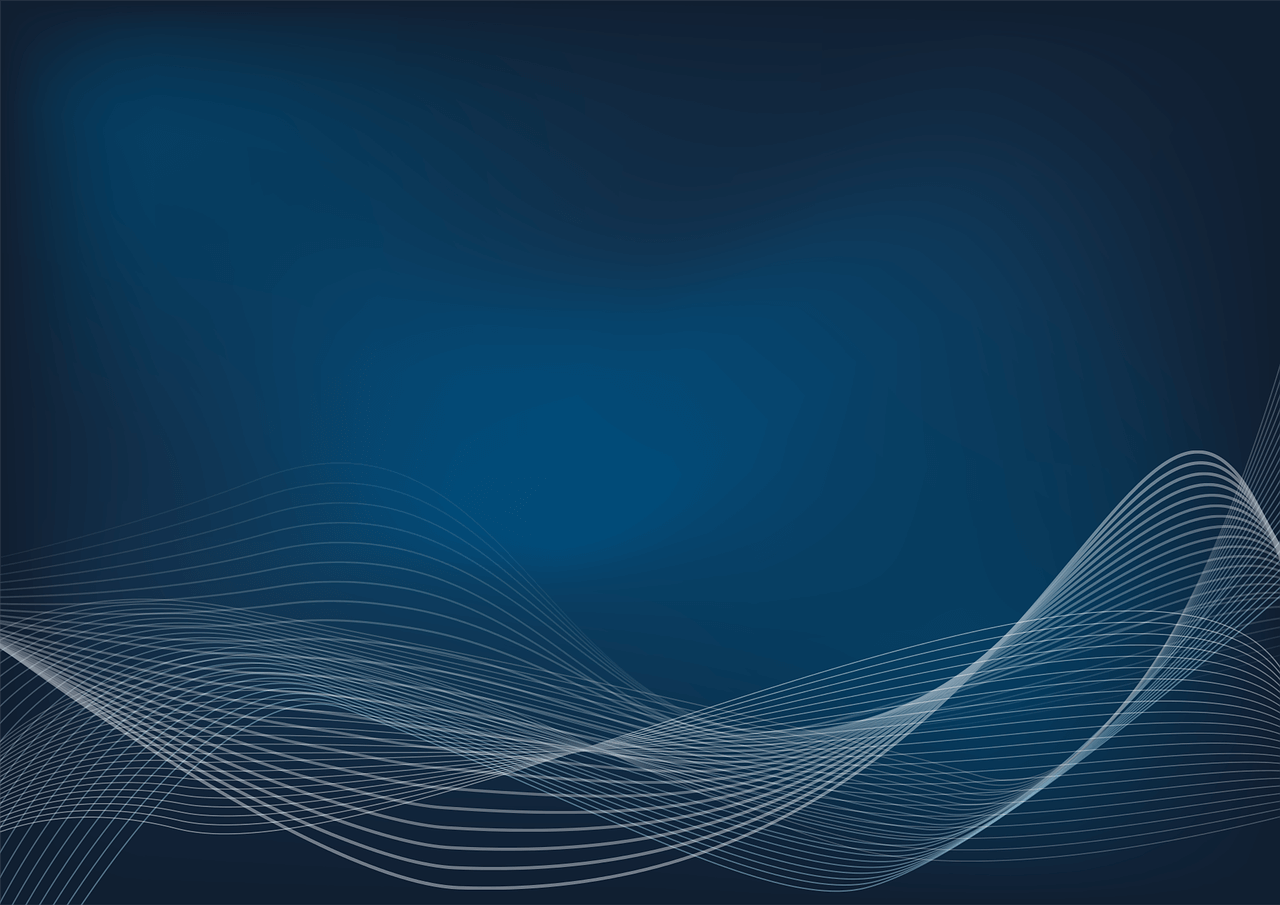― 三原則 ―
前稿で述べたが、日本人は「三つに括る」のが好きといえる。身近な所では、松竹梅や福禄寿、甲乙平、三種の神器、三冠王、3Kなど三つに括った言葉が多く存在する。
そして、ビジネスに関しても先人の残した多くの三原則や三条件・三要素などが存在する。以下その三原則などについても一部を紹介したい。
1.ビジネスの三原則
仕事の三大要素は「計画、実行、確認」と言われている。「PDCAを回す」など仕事をする上ではよく言われることであるが、それと同じようにビジネスの三原則として、「ヒト・モノ・カネの三原則」「人を動かす三原則」などもよく聞く。
・「ヒト・モノ・カネの三原則」とは、ビジネスを成功させるには、ヒト・モノ・カネの三要素を活かすこと、即ち「人的資源であるヒトを活かす」、「物的資源であるモノを活かす、「資金であるカネを活かす」のが原則である。
・「人を動かす三原則」は、デール・カーネギーの著書『人を動かす』で紹介されている 「批判も非難もせず、苦情も言わない」「率直で、誠実な評価を与える」「強い欲求を起こさせる」が有名であるが、山本五十六の「言って聞かせて、やって見せ、褒めてやる」や荻生徂徠の「人を用いる道は、その長所を取りて短所はかまはぬことなり」も人を動かす格言である。カーネギーは「人を思い通りに動 かすたった一つの方法は、相手が欲しいものを与えること、そのように動機付け、機会を与える事」とも言っている。
・「モノを活かす」とは、モノの持つ価値・機能をそれを欲している人に与えられるようにすること。付加価値をつけて提供すること、長く使う事である。
・「カネを活かす」原則については、フランシス・ベーコンは、「金は肥やしのようなもので、撒かなければ役に立つことはない」と言った が、どのように撒き、肥やしにする方法は千差万別である。ヘンリーフォードが言うように「財産は来るもので、作るものではない」、お金は追いかければ逃げていき、お金を引き寄せるためには、社会に貢献すれば良く、そうすればお金の方からやってくると言われている。この格言のように「世の中に役立つモノにつかうこと」が「カネを活かす」王道であろうが、「最小経費で最大利益を生むこと」が経理的にはカネを活かすことであると捉えられている。
最近のものでは、政府や経団連が推進する技術革新により国際競争力の強化と社会課題の解決の両立を目指す「Society「5.0実現ビジネスの3原則」は、①「革新的なビジネスモデルを創る」、②「優れた製品・サービスを開発するために、イノベーションを通じて不断に新たな知を創る」、③「新たな市場を創出するために、SDGsの視点を反映させて、国際競争力の向上に資するルールを創る」というものがある。
2.その他の三原則
・「行動の三原則」では、①すぐやる! ②必ずやる! ③仕上がるまでやる/出来るまでやる
・業務改善の3原則では、「やめる、減らす、変える」
・現場の三原則では、安全の三原則、三現主義、現場再建の3原則があり、
安全の三原則は、安全はすべてに優先する、自分の身は自分で守る、「ルールを守る。安全管理をしっかり行うことで、現場の空気が変わり、工程や品質も良くなる。
三現主義は、現場、現物、「現実。現場に足を運び、現物に触れ、現実を把握した上で物事を考える。
現場再建の3原則は、時を守り、場を清め、「礼を正す。これにより職場における秩序の乱れや効率の低下を改善するために役立つ。
・顧客満足の三原則は、商品(鮮度・品質の良さ、顧客要求に応える機能・豊富な種類)、サービス(親切な接客と購入後のフォロー)、店舗(利便性が良く、清潔できれいな売り場)からホスピタリティ(もてなしの心)、エンターテインメント(驚くような感動をもたらす)、プリヴァレッジ(特別待遇)の顧客満足の新三原則になった。
・商売の三原則は、「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」や、「稼ぐ・削る・防ぐ」の「か・け・ふ」
・経営の三原則には、社会への貢献、個人の尊重、商業的合理性の追求がある。
・帝王学の三原則は、①原理原則を教えてくれる師を持つこと、②直言してくれる部下を持つこと、③良き「幕賓」を持つこと
恐ろしい三原則では、
滅びる会社の三原則(福永雅文のWeb)というのもあり、①理想を失った会社は滅びる、②すべての価値を物やお金に置き換え、心の価値を見失った会社は滅びる、③自社の歴史を忘れた会社は滅びる。というのもある。
(MOTIP 新家;nt-pro.office@ja3.so-net.ne.jp)