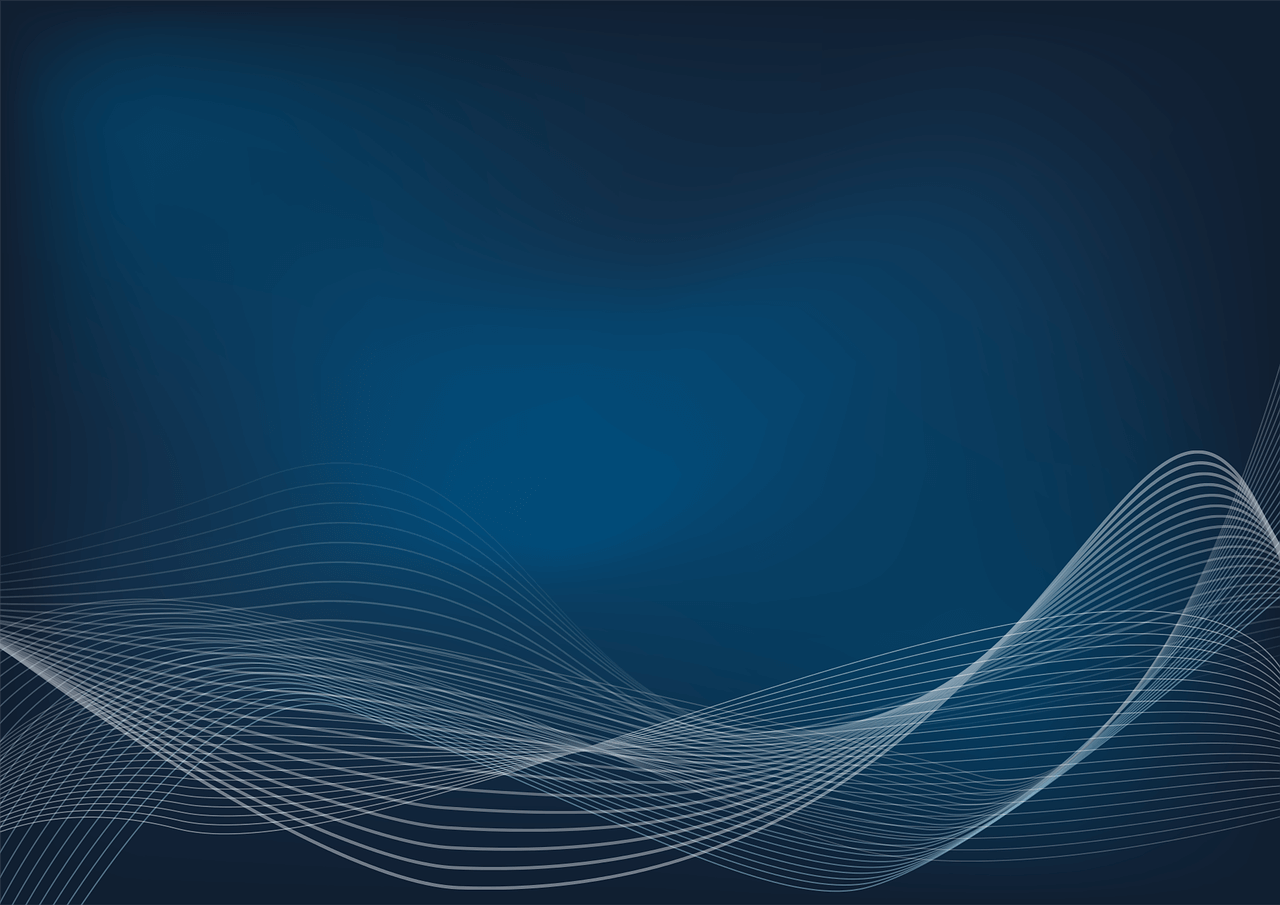― 三つに纏めることで思う事 ―
「四十、五十は洟垂れ小僧、六十、七十は働き盛り、九十になって迎えが来たら百まで待てと追い返せ」は渋沢栄一の言葉といわれている。前稿で述べたように、日本人はこのように「三つに括る言葉」が好きといえる。「3」という数字は日常の先人言葉の中でも、またビジネスの世界でも目に付く。
例えば、日常の生活のなかでは、
「三」や「3」が付く言葉は、昔からの諺等に多く見られ、例えば以下のものが挙げられる。
・三つ子の魂百まで ・石の上にも三年・桃栗三年柿八年 ・三人寄れば文殊の知恵 ・二度あることは三度ある ・三度目の正直 ・早起きは三文の徳 ・仏の顔も三度まで、等。
また、日本において、「3」という数字は縁起の良い数字と見なされているのは、以下の例が示している。
神前結婚式では、「三々九度」。大・中・小の3つの盃を使用して、新郎新婦がお酒を酌み交わす儀式で、1つの盃で3回お酒を酌み交わし3を重ねる。
「手締め」と呼ばれる日本独特の儀式として、「一本締め」や「三本締め」等があるが、「一本締め」は、手を3回・3回・3回・1回と打つことを1セットとし、これを3セット行うものが、正式な手締めとされる「三本締め」となっている。(因みに、手を1回だけ打つのは「一丁締め」と呼ばれ、これは「関東一本締め」とも呼ばれて、一本締めと混同されているケースが多いようだ)。
また、「三々七拍子」もめでたい席で行われ、手を3回・3回・7回を1セットとして行われる。手を打つ回数がなぜこのような構成になっているのかについては、それぞれに対して由来があるようだが、いずれにしても数字の「3」がベースになっており、これは数字の「3」が縁起の良い数字だということが関係しているものと推定されている。「万歳三唱」も、各種の祝賀活動等において、万歳を3回繰り返すのはよく経験する。
縁起の良い短い言葉では、松竹梅や福禄寿、など三つに括った言葉が存在するが、「3」は日本人にはなじみのある数字である。
また、ビジネスに関しても先人の残した多くの三つに括った原則や三条件・三要素などが存在することは、以前の稿で紹介したが、ビジネスにおいても「3」と言う数字はキーワードになっている。
たとえば、プレゼンテーションにおいても、「理由を三つに纏めると」とか「メリットを三つ上げると」とか「経営施策を三つに要約すると」とかが良く使われ、重要であるとよく聞く。
ロジカルシンキングでも「三つの思考法」、「三つの基盤スキル」、「三つのツール」がキーワードになって、ゼロベース思考、フレームワーク思考、オプション思考やツールではロジックツリー、マトリックス、プロセスが知られている。
何故「3」なのかであるが、人は情報が多いと記憶も理解もし難いが、三つに整理されていると理解も記憶もしやすいと言われており、格言や先人の言葉も三つに整理されて使われ残っているようだ。
5W1Hも、まずは「誰に」「何を」「どのように」の視点を優先して取り組む(シナリオを構成する)のが良いと言われているが、ここでも、三つの括りがキーである。
「種まき期」、「水やり期」、「収穫期」と区分けされた「3年サイクル」という考え方も先人に広く普及しており、企業の中期計画も3年間で設定されているのが多い。
欧米でも、「3」はキーワードになっている。カウントダウンは「3・2・1」であり、リンカーンの有名な言葉も「人民の・人民による・人民のための政治」と「3」で括っている。
ドラッガーは利益を上げるアプローチとして、①マーケティング、②イノベーション、③生産性向上の三つが重要であると言っている。
「三」に過度に捕らわれず、自分なりの考えを持つことが一番の原則という先人もいるが、経営者や投資家を動かす「短く、魅力的な」プレゼンは、無駄な情報がそぎ落とされたものが必須であり、企画書・報告書の作成でも「3」を意識して纏めるのが大切である。
(MOTIP 新家;nt-pro.office@ja3.so-net.ne.jp)